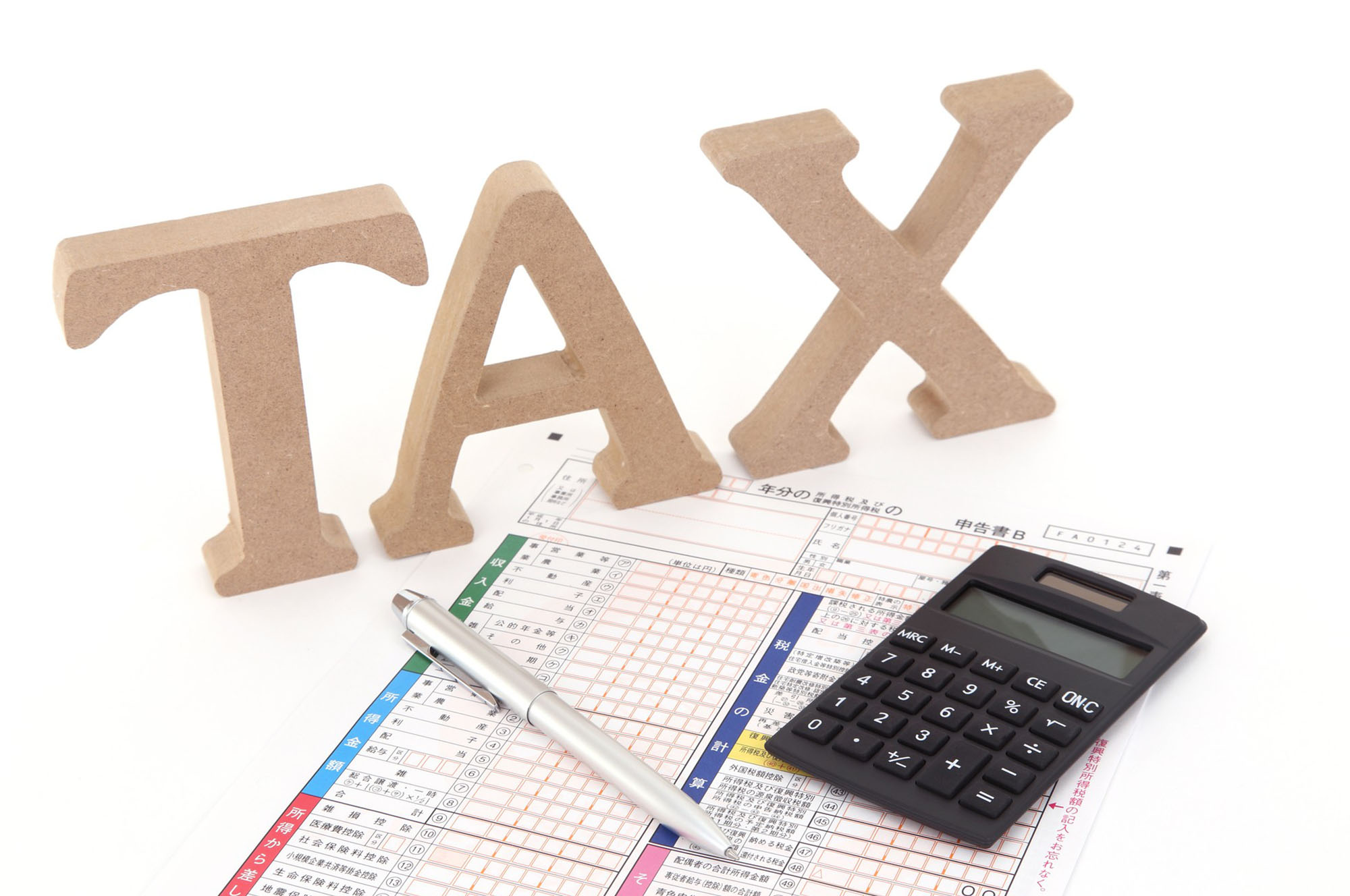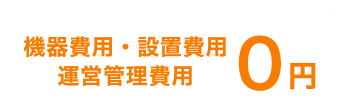駐車場経営で得た収入に確定申告は必要?
駐車場経営で得た収入に対して確定申告が必要かどうかは、年間の所得額によって決まります。給与所得者の場合とそれ以外の場合で確定申告が必要な年間の所得の額が異なります。
| 項目 |
年間所得額 |
確定申告 |
| 給与所得者(会社員やアルバイト・パートほか)の副業 |
副業の所得年間20万円以内 |
不要 |
| 副業の所得年間20万円超 |
必要 |
| 給与所得者以外(個人事業主やフリーランスほか) |
総所得年間48万円以内 |
不要 |
| 総所得年間48万円超 |
必要 |
確定申告とは、個人事業主や自営業、給与所得者である個人でも申告が必要な人が1年間(1月1日から12月31日まで)に得た全ての所得と、それに対する所得税額などを計算して確定し、税務署に申告・納税する手続きのことを指します。
近年、副業を認める企業が増え、会社員として給与を得ながら、副業で収入を得ている方も多くなってきています。そのため、給与所得者でも確定申告が必要になる方もいます。その場合の確定申告の所得区分は、一般的な給与所得者が副業で得た収入の額によって、以下のように判断されます。
| 雑所得 |
年間所得20万円超~300万円以下 |
| 事業所得 |
年間所得300万円超(事業所得の可能性高) |
給与所得者が年間20万円超~300万円以下の副収入を得た場合は、雑所得として確定申告が必要です。また、副業であっても所得が300万円を超える場合は社会通念上、事業所得と判断されることがあります。ただし、給与所得者でない場合、副業を含めた全ての所得の年間合計額が基礎控除額の48万円以下であれば、確定申告は必要ありません。
所得は、以下の式で表されます。
(所得)=(総収入)-(必要経費)
たとえば副業による収入が30万円あっても、必要経費が15万円であれば所得は15万円となり、もともと確定申告の必要のない給与所得者の場合、確定申告は必要ありません。しかし、医療費控除や住宅ローン控除などを受けるために確定申告をする場合は、副業の所得が20万円以下であっても申告が必要です。

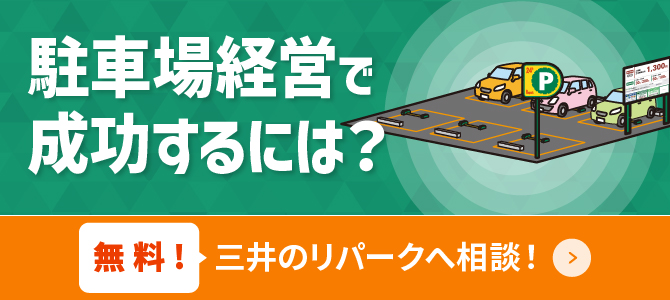
駐車場経営にまつわる3種類の所得区分
所得税法では、所得をその性質に応じて10種類に分類しています。駐車場経営に関連する主な所得区分は、以下の3つです。
・不動産所得
・事業所得
・雑所得
以下でそれぞれについて詳しく見ていきましょう。
不動産所得
不動産所得とは、土地や建物などの不動産から得られる所得のうち、以下のようなものを指します。
・土地や建物などの不動産の貸し付け
・借地権など不動産の上に存する権利の設定および貸し付け
また、船舶や航空機も不動産に該当するため、その貸し付けも不動産所得になることを覚えておくとよいでしょう。
事業所得
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業といった事業から生じる所得のことです。事業所得には青色申告することで最大65万円の特別控除といった税制上の優遇措置があります。また、青色申告や白色申告にかかわらず、事業所得や不動産所得は、赤字が発生しても給与所得等ほかの所得との「損益通算」ができ、課税所得を減らすことが可能です。損益通算とは、赤字が発生した場合にほかの所得から損失分の金額を控除することを指します。
不動産の貸し付けによる所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得と判断されます。また、不動産所得が事業的規模であっても単なる不動産の貸し付けによる所得であれば、不動産所得に該当します。
雑所得
雑所得とは、ほかの9種類のいずれにも該当しない所得のことを指し、たとえば、年金や恩給などの公的年金、FXや暗号資産取引で得た利益、非営業用貸金の利子などが該当します。また、雑所得の場合、青色申告特別控除による最高で65万円の控除や、損益通算制度を利用できない点には注意が必要です。

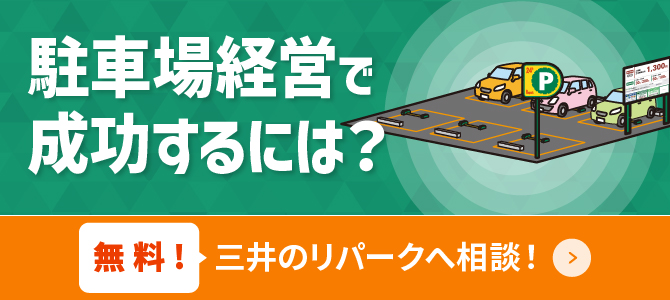
駐車場収入はどの所得区分に当てはまる?
駐車場経営による収入がどの所得区分に該当するかは、その運営形態によって異なります。判断基準となるのは以下の2つです。
・管理責任の所在
・事業的規模
管理責任の所在とは、駐車場の管理責任が賃貸人にあるか否かということです。管理責任の所在によって駐車場収入の区分は以下のように変わります。
| 賃貸人が管理責任を負わない場合 |
不動産所得 |
| 賃貸人が管理責任を負う場合 |
事業所得または雑所得 |
事業的規模には、明確な判断基準が設けられておらず、一般的には、社会通念上「事業」と称するに至る程度の規模で、独立・継続・反復して行われているかどうかで判断されます。賃貸人が管理責任を負う場合で、事業的規模であれば事業所得、事業的規模でなければ雑所得です。
たとえば、以下の2つの例では、それぞれ適用される所得区分が異なります。
| 比較項目 |
所得区分 |
運営形態 |
賃貸人が管理責任を
負わない場合 |
不動産所得 |
月極駐車場として土地を貸しているだけ
(駐車場運営会社による一括借り上げ方式による運営も含む) |
賃貸人が管理責任を
負う場合 |
雑所得 |
事業規模と見なされない50台未満のコインパーキングを運営 |
| 事業所得 |
事業規模と見なされる50台以上のコインパーキングを運営 |
土地を貸しているだけの場合
土地を月極駐車場として貸し付けている場合、多くは不動産所得に該当します。管理責任を負わず、単に土地を貸し付けて地代収入を得ているだけであるのが理由です。ただし、貸し付けが一時的なものであり、継続性や反復性がない場合、雑所得と判断されることもあります。
また、土地を駐車場運営会社に貸し、一括借り上げ方式によって駐車場を運営している場合も、不動産所得に該当します。
管理運営を自分で行っている場合
賃貸人(土地所有者)が自ら(業務を委託していても責任を賃貸人が負う場合も含む)駐車場の管理・運営などの管理責任を負い、かつ事業的規模で駐車場経営を行っている場合は、事業所得として認められる可能性が高いです。たとえば、多くの駐車スペースを提供し、料金収受、清掃、トラブル対応などを自ら行い、積極的に運営している場合(業務を委託していても責任を賃貸人が負う場合も含む)は、事業所得に該当するでしょう。
一方、駐車場運営を賃貸人が行い、管理責任を負っている場合で、事業的規模に該当しない場合は雑所得と見なされます。
たとえば、コインパーキングのような時間貸し駐車場の場合には、総合的な視点で事業所得か、雑所得かを判断する必要があります。判断のポイントとしては、駐車場の利用状況によって収入が変動するか、車止めや精算機などの駐車場設備は誰が所有するか、管理運営の責任は土地の所有者・駐車場事業者の誰が負っているのかなどが挙げられます。

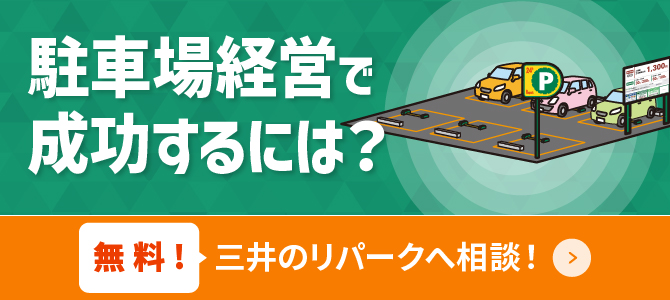
駐車場経営で経費にできるもの
確定申告の際、駐車場経営で得た収入から、必要経費を差し引いた金額を所得金額として申告することが認められています。必要経費を差し引くことで、課税所得を抑えられ、結果的に所得税が減ることになります。駐車場経営で経費として認められる主な費用は大きく以下の2つに分けられます。
・初期費用
・運営費用
以下でそれぞれについて詳しく見ていきましょう。
初期費用
駐車場経営を開始するために必要な費用は取得費として費用計上でき、具体的には以下のようなものが挙げられます。
・土地の整地費用
・アスファルト舗装費用
・ライン引き費用、車止め、フェンス、看板、監視カメラなどの設置費用
・精算機の設置費用
ただし、10万円を超えるものは一括での費用計上はできず、減価償却費と見なされます。減価償却費は、それぞれに定められた耐用年数に応じて分割して経費計上が可能です。
運営費用
駐車場経営を運営中に発生する以下のような費用も、経費として計上できます。
・駐車場用地(土地)の固定資産税、都市計画税
・管理会社・運営会社の委託費
・電気代
・利用者募集の広告宣伝費
・清掃費用
・修繕費用
・損害保険料
上記以外にも、駐車場経営に関連する費用であれば、税理士や弁護士への相談費用等も経費として認められることがあります。経費計上する際には、領収書や請求書などの証明書類が必要になるため、きちんと保管しておくことが重要です。

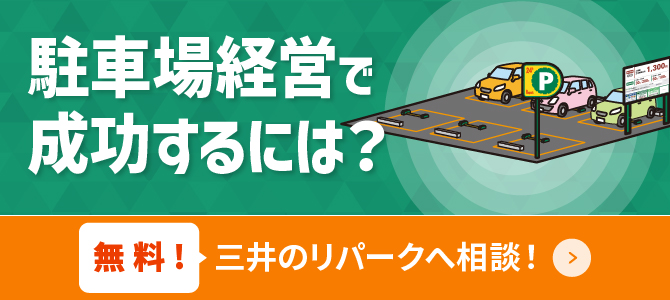
駐車場経営の確定申告の方法
確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。
青色申告では、複式簿記による帳簿付けが義務付けられていますが、10万円、55万円、65万円の青色申告特別控除など、税制上の優遇措置を受けることができます。また、65万円控除を受けるには、不動産所得なら事業的規模かつe-Taxによる申告(電子申告)または優良な電子帳簿の保存の要件を満たすことが必要です。
不動産所得が事業規模と判断される基準として「5棟10室基準」があり、一戸建てなら5棟、アパート等なら10室以上の貸室を所有していると事業的規模に該当します。駐車場の場合、5台でアパート等の1室に相当するため、駐車場だけで50台以上の貸し駐車スペースを所有していると、事業的規模と見なされます。
青色申告とするには、事前に税務署に「青色申告承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があるため注意が必要です。申請書を提出し、承認を受ける場合、青色申告で申告したい年の3月15日までに申請書を提出しなければなりません。なお、青色申告するためには、不動産所得か事業所得を得ている必要があります。
青色申告の承認を受けていない場合は、自動的に白色申告となります。白色申告では、収支内訳書の作成や簡易的な帳簿付けで済みますが、青色申告のような特別控除は受けられません。駐車場経営で一定の収入がある場合は、事業的規模でなくても節税効果の高い青色申告がおすすめです。

確定申告の手順
青色申告による確定申告の手順は以下の通りです。
1.青色申告承認申請書の提出(青色申告したい年の3月15日までに提出)
2.記帳、帳簿の作成(複式簿記で)
3.確定申告書の作成
4.申告書の提出・納税(原則翌年の3月15日まで)
青色申告で必要となる複式簿記は専門知識が必要となるため、知識がない場合は会計ソフトの利用や税理士への依頼を検討しましょう。提出期限までに申告・納税を行わないと、加算税や延滞税が課される場合もあります。申告書の提出は期限内に行えるよう、事前に準備しておきましょう。
駐車場経営は一括借り上げ方式がおすすめ
小規模の駐車場経営では、一括借り上げ方式による運営がおすすめです。一括借り上げ方式とは、土地所有者が駐車場運営会社に土地を一括して貸し、運営会社が駐車場を運営・管理する方式です。手間がかからない点や初期費用が不要である点、駐車場の稼働状況にかかわらず、毎月一定の賃料を受け取れる点が魅力です。
たとえば、相続した被相続人の住宅や土地を整備して駐車場経営を始める場合、住宅用地であることが多いでしょう。このような場合、その土地だけなら事業規模がそこまで大きくないことから、自主運営することも可能です。ただし、自主運営では、初期費用や手間がかかるだけでなく、運営中の管理責任も負わなければなりません。そのため、収入は自主運営に比べると下がりますが、相続した住宅用地を活用した小規模の駐車場経営であれば、初期費用もほとんどかからず、運営の手間もない一括借り上げ方式がおすすめです。
また、確定申告については、一括借り上げ方式であれば管理責任がないことから駐車場経営で得られた所得は不動産所得に該当します。不動産所得の場合、青色申告することができ、規模が小さくても10万円の青色申告特別控除を受けることができます。自主運営の場合、規模が大きくなければ雑所得になり、青色申告が受けられないことを考えると、不動産所得に該当する一括借り上げ方式のほうが確定申告上、メリットがあります。

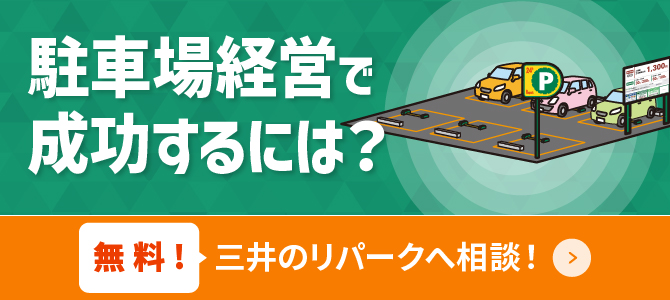
駐車場経営を始めたい方は一括借り上げ方式の三井のリパークへお任せください
ここまで、駐車場経営に該当する所得の種類や所得区分による申告上の特徴、確定申告の方法などを解説してきました。できるだけ経費や手間を少なくして駐車場経営を行いたい人には駐車場運営会社による一括借り上げ方式がおすすめです。一括借り上げ方式の駐車場経営は、効率的に安定した収入を得られる土地活用方法といえます。
三井のリパークでは一括借り上げ方式や運営をお任せいただく管理委託方式などさまざまな方式で、オーナーさまに合った駐車場経営をご提案しています。特に、一括借り上げ方式であれば、オーナーさまに駐車場経営に必要な設備や機器のご負担などがなく、運営の手間もかからずに土地活用が可能です。なお、希望日の2ヵ月前までの告知により解約が可能なため転用性が高く、一時的な駐車場運営もできるというメリットがあります。(※1)駐車場経営に関してお困りの方は、三井のリパークへ、お気軽にお問い合わせください。
※1 立地等によってはお受けできない場合もございます。また、建物解体、アスファルト舗装、外構、固定資産税などの租税公課や町内会費はオーナーさまのご負担となります。